ケンカの中身は「文学的」じゃない?仲が超悪かった日本の文豪たち

日本を代表する文豪・太宰治は芥川賞に落選した際、選考委員だった川端康成に「刺す」「大悪党だと思った」など、殺害予告にも近いような怒りの抗議文を送った。
というのも川端は芥川賞の選考で、当時薬物中毒などに陥っていた太宰の生活ぶりがよろしくないとの理由で太宰の作品を評価しなかったからだ。
才能のある作家というのは気難しい性格が多いようで、文豪たちの間ではもめごとが生じていたり、不仲がささやかれたりすることが多い。その内容はゴシップ的なものから文学的意義の高いものまで様々である。
今から紹介する以下の3つのケースなどは、作家同士の複雑な関係を示す代表的な例と言えるだろう。
画像をもっと見る
①問題児「中原中也」と、お騒がせキャラ「太宰治」
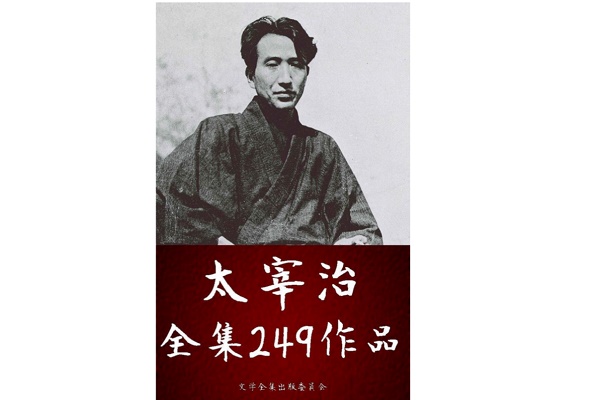
画像出典:Amazon
太宰治は先ほどの川端康成の件だけではなく多くの作家との確執を持ち、作家人生から私生活に至るまでお騒がせキャラというべきか何かと問題の多い作家だった。
一方、夭折の天才詩人である中原中也も相当な問題児として知られている。酒癖は非常に悪く、他の作家を殴ったり暴言を吐いたりなど素行に難が多い作家である。
太宰が友人の作家・檀一雄と一緒におでん屋に行ったときのことだった。その場に居合わせた中原が太宰と話しているうちにだんだん酔いがまわり、すさまじい悪絡みをするようになっていった。
「何だい、おめえの好きな花は」と問いつめられた太宰が今にも泣きだしそうな声で「モ、モ、ノ、ハ、ナ」と答えると、中原は「チェッ、だからおめえは」と太宰を小ばかにし、ふたりの関係に亀裂が生じる。
檀は太宰の没後に執筆された『小説 太宰治』の中でそのときのふたりのやりとりを記しているが、中原はそんな壇のことを「太宰の腰巾着」と罵った。
太宰も太宰で友人に対し中原の人間性を「とても付き合えた代物じゃない」と見下していたようだがそれはもうしょうがない。
関連記事:「初デートでクーポン」に幻滅する女性の割合が判明!バレない抜け道も?
②一方的に攻撃? 菊池寛ウォッチャー「永井荷風」
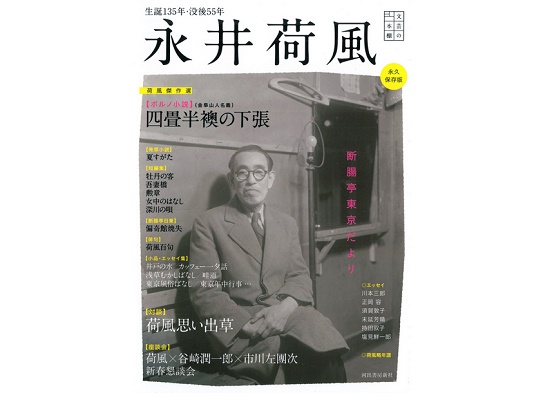
『あめりか物語』などで知られる永井荷風は菊池寛をとても嫌っており、荷風の日記作品『断腸亭日乗』には菊池への壮絶な悪口が多く記されている。
「悪むべきは菊池寛の如き売文専業の徒のなす所なり」といった罵倒に始まり、面会を求めた菊池を「交を訂すべき人物にあらず」とはねつけ、菊池から年賀状が届いた際にはわざわざ送り返している。
酒館の女給の人気投票に参加する菊池を「田舎者」と罵るなど、もはや菊池寛ウォッチャーともいうべき姿勢で一方的に攻撃しっつづける荷風。しかもこれらの悪口は氷山の一角。
群れることを嫌って文壇と距離を置くようにしていた荷風にとって、芥川賞や直木賞、文藝春秋社の創設によって文壇の中心にいた菊池の商業的な姿勢が受け入れられるものではないという部分が大きかったのだ。
関連記事:【変人ばっかり】童貞? 風呂嫌い? あの文豪たちの知られざる意外な一面とは
③出版社を巻き込んで揉めた「三島由紀夫」と「松本清張」

『金閣寺』『仮面の告白』などの作品で知られる三島由紀夫は、恵まれた家庭で生まれ育ち、16歳の若さで作家デビュー。早熟の天才として瞬く間に文壇のスターとなった。
一方の松本清張は貧乏家庭で育ち、印刷所勤務や徴兵、新聞社勤務やアルバイトを経て40歳でようやくデビューし、『点と線』などの社会派ミステリを書いて遅咲きの人気作家となる。
正反対の経歴を持つふたりが、仲違いしたきっかけは昭和36年。
ある出版社が新しく刊行しようとしていた文学全集の監修に三島の姿があった。出版社側が当時流行作家であった清張の作品を収録しようと企画したところ、清張の作品を評価していなかった三島がそれを強硬に突っぱねたのだ。
「清張には文体がない。推理小説は文学と認められない!」とまで言い張った三島を説得しようとしたのが川端康成。川端は清張の文学的才能を高く評価していた。
しかし三島も折れることなく、最後までお互いの意見を譲らなかったふたり。出版社の社長まで巻き込む事態となり、結局清張の作品は収録が見送られる。
それから9年後の昭和45年、三島が市ヶ谷駐屯地で自決。その後の三島の印象を尋ねられた清張は「彼の才能は枯渇していた」と三島の文学的才能を叩き斬った。
このように文豪たちのケンカは俗っぽくもあれば文学者のプライドを感じられたりと、その内情はさまざま。
そういった背景から多くの名作が生まれてきたのだとすれば、いち読者としては「いいぞ、もっとやれ」と炊きつけたい気分に駆られてしまう。
(文/しらべぇ編集部・星井七億)













